お知らせ
【CANVAS NEWS】2025年8・9月号
2025年8・9月号 誌面

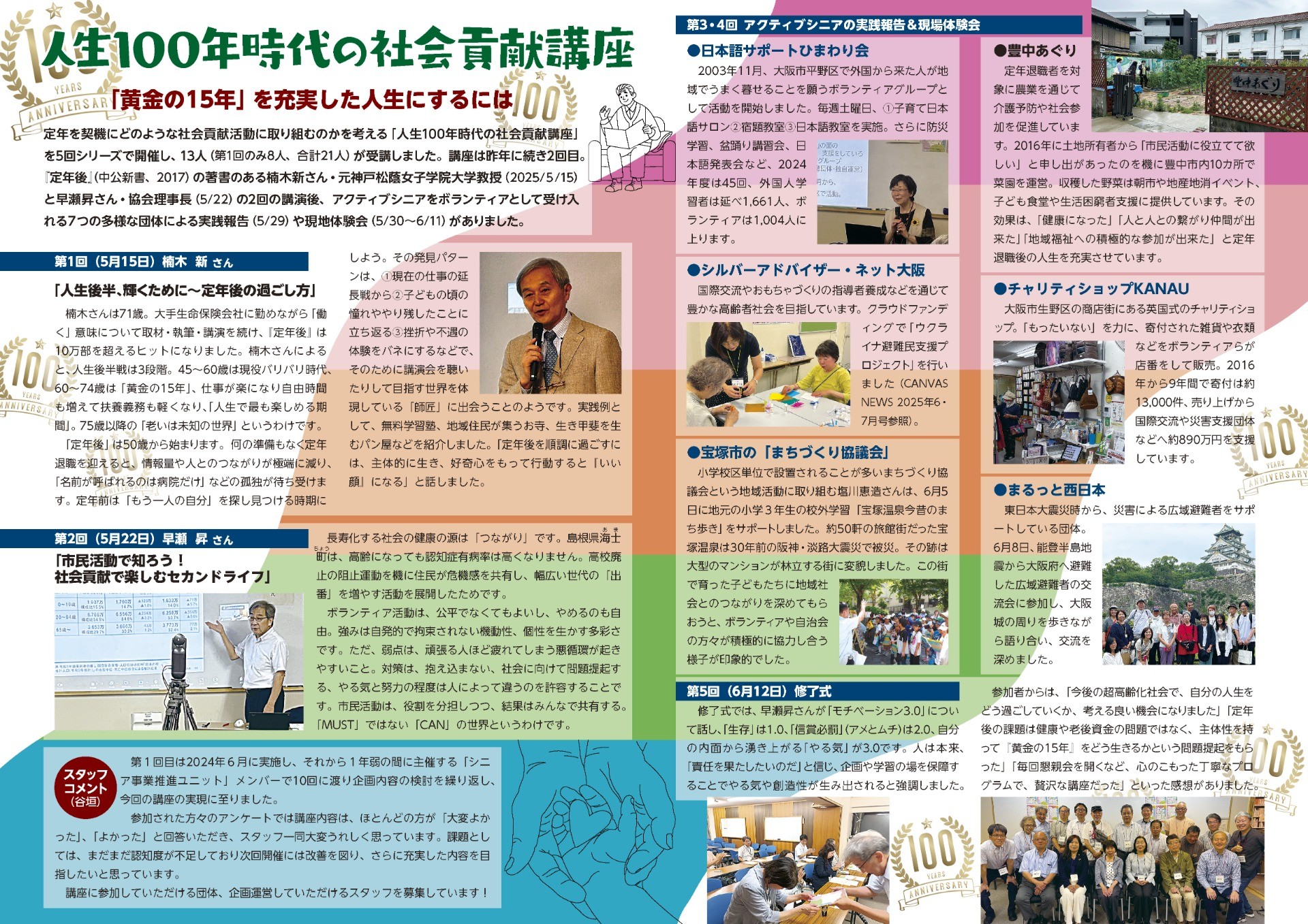

社会課題の解決に向き合うNPO メールインタビュー全文
認定NPO法人 日本レスキュー協会 松﨑 直人さん
1.団体設立のきっかけや経緯を教えてください。
1995年1月17日、阪神・淡路大震災により6,434名の尊い命が失われました。この自然災害の猛威に日本中が言葉を失う中、海外から多くの支援とともに行方不明者を捜索する犬たちも駆けつけました。この活躍を目の当たりにして、素晴らしい能力を持つ犬たちが日本にも存在していたならば救われた命があるかもしれないと、犬を使った人命救助に特化した組織の重要性を実感し、その年の9月1日(防災の日)に日本レスキュー協会は誕生しました。

2.団体の活動内容について簡単に教えてください。また、団体の節目の出来事を時系列(西暦年)に沿って教えてください。
日本レスキュー協会は3つの事業を中心に活動をおこなっております。①「災害救助犬」②「セラピードッグ」③「動物福祉」災害救助犬は国内外の災害が発生すれば行方不明者の発見の為、救助活動に出動します。過去には発足して直ぐにメキシコ中西部沖地震が発生し、初出動となりました。また1999年には大地震が多い年で8月17日トルコ北西部地震、9月21日台湾大地震、11月12日トルコボルー地震と出動が多い1年となりました。2024年には能登半島地震、能登半島豪雨災害への出動も行っております。

- 3.団体として大切にしている思いや、ミッションについて教えてください。
「犬とともに社会に貢献する」という理念のもと活動しております。
4.災害救助犬やセラピードッグとして活動するためには、どのような認定試験や育成過程があり、それぞれの育成にはどのくらいの期間や費用がかかるのでしょうか。
災害救助犬とセラピードッグの訓練はそれぞれで実施しており、認定試験をおこなっております。災害救助犬については、行方不明になった人を探す捜索訓練、ハンドラーの指示を聞く服従訓練、高所訓練、はしごを渡る訓練、環境馴致訓練、遠隔訓練、輸送訓練など様々な訓練を行っております。育成には約3~4年かかり、出動できる割合は3~4割と狭き門です。育成費用は1000万円ほどになります。
5.団体の運営や事業の実施において課題を感じていることがあれば教えてください。
このような活動は皆様のご支援で活動ができております。多くの方に活動を知っていただくことが必要です。一人でも多くの命を救いたい、助けたいという思いで、阪神・淡路大震災での経験を活かし、災害に対応していく訓練や育成に取り組める環境を整えていきたいです。

6.今後の展望についてお聞かせください。
近年、災害が多くなってきております。地震や豪雨災害など頻繁に発生してきているので災害に備え、災害救助犬の育成・派遣、セラピードッグの育成・派遣、また避難所でのペット支援やペット防災についての啓発や取り組みをおこなっていきたいと考えています。災害時に一人でも多くの命を救えるように。

NPO法人 えんぱわめんと堺/ES 北野 真由美さん
- 1.1997年にグループを発足されたと拝見しました。活動に至ったきっかけを教えてください。北野様は、もともとお仕事等で子どもたちと関わる機会がおありだったのでしょうか。
特に子どもに関わる仕事をしていたわけではありません。子育てをしながら、国際交流でホームステイの受け入れなどをしていました。海外から来た子どもたちと生活を共にし、関わっている中で、海外での子どもの教育や家庭でのあり方、子どもに関わるすべての事に関心が高まりました。子育て中で、子どものいじめや暴力、またおとなからくる誘拐など、どのようにすれば子どもが被害にあわないか、加害もしないようになるのかを常に考えていた中で、海外の子どもに関わるプログラムに着目しました。
2.CAPプログラムは参加型とのことですが、実際にロールプレイやトークタイム、レビュータイムを行う際に、特に意識していることや大切にされていることがあれば教えてください。
子どもに対しての子ども観を大事にしています。特に子どもを一人の人として向き合うように心がけ、子どもの人権・権利について意識をしています。

3.ワークショップの中で印象的だった子どもたちの反応やエピソードがあれば、お聞かせください。
これまで長年の活動の中で数知れぬ、子どもの反応やエピソードがあります。特に、「死にたい」と話してきた子どもがエンパワメントの関わりで、ワークショップを終えたあとに変化してきたようすや表情は複数、心に残っています。

4.子どもたちが自分を守る力を身につけるためには、日常生活の中で大人はどのようなサポートができるでしょうか。
まずは、聴く。子どもを主体に子どもの話や一人ひとりの子ども理解をする中で、常に子どもの話を聴く時間や場は、不可欠だと考えています。
5.活動を続けるうえで感じる課題はどのようなものですか。また、今後さらに取り組まれていきたい課題があればお聞かせください。
子どもを権利の主体として、向き合うおとな社会になっていないこと。
子ども基本法が動いているにも関わらず、子ども権利条約が浸透していない。
子どもに関わる人すべて、そして子ども自身に子どもの権利を周知すること。
子どもが自分のからだや気持ちを、日常の生活の中で肯定的に受け止める環境や教育が足りない。

6.今後の展望についてお聞かせください。
6でも記したこと以上に、子どものことを取り組むときに、もっと子どもの声を聴くおとなを増やすこと(良い聴き手として)。



 寄付・寄贈する
寄付・寄贈する 寄付する
寄付する 会員になる
会員になる

