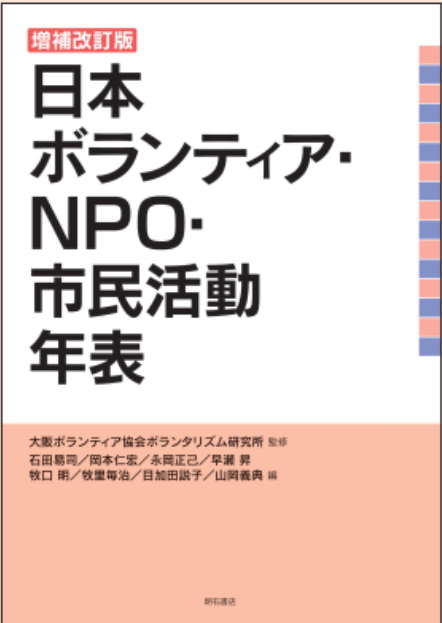調査・研究・政策提言
Research, Analysis and Advocacy

ボランタリズム研究所
ボランタリズム研究所は、大阪ボランティア協会の
調査研究機能を特化し2009年10月に開設されました。
個人および組織のボランタリズムの思想・原理に依拠するボランティア活動/市民活動は、
21世紀日本社会の平和、民主主義、市民社会のありかたを左右するであろうとの認識に立ち、
また、国際的視野に立ちつつ、日本の市民活動あるいは
ボランティア活動を支える原理や理念のさらなる追求と、
それらの実践的プログラムの開発など理論的科学的な研究を目指します。
研究誌
-
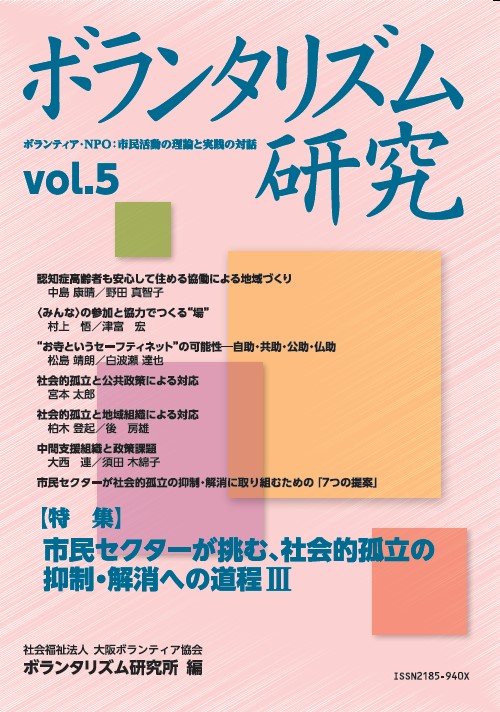
ボランタリズム研究
―Vol.5―特集
市民セクターが挑む、社会的孤立の抑制・解消への道程Ⅲ
発行年2023年10月
「市民セクターの次の10年を考える研究会」第2幕の下記回についてまとめています。
-
第11回 認知症高齢者も安心して住める協働によるまちづくり 2019/9/23
講師
中島康晴さん(特定非営利活動法人地域の絆代表理事)
野田真智子さん(株式会社芳林社「Better Care 」編集長) -
第12回 <みんな>の参加と協力でつくる“場” 2019/11/2
講師
村上 悟さん(特定非営利活動法人碧いびわ湖代表理事)
津富 宏さん(静岡県立大学国際関係学部教授) -
第13回 “お寺というセーフティネット”の可能性-自助・共助・公助・仏助- 2020/1/13
講師
松島靖朗さん(安養寺住職、認定NPO 法人おてらおやつクラブ代表理事)
白波瀬達也さん(関西学院大学人間福祉学部教授) -
第14回 社会的孤立と公共政策による対応 2021/7/18
講師
宮本太郎さん(中央大学法学部教授、生活困窮者自立支援全国ネットワーク顧問)
-
第15回 社会的孤立と地域政策による対応 2021/9/18
講師
柏木登起さん(一般財団法人明石コミュニティ創造協会常務理事兼事務局長、 NPO 法人シミンズシーズ代表理事)
後 房雄さん(愛知大学地域政策学部教授) -
第16回 中間支援組織と政策課題 2022/3/31
講師
大西 連さん(認定NPO 法人自立生活サポートセンター・もやい理事長、 内閣官房孤独・孤立対策室政策参与)
実吉 威さん(公益財団法人ひょうごコミュニティ財団代表理事) -
同時収録 市民セクターが社会的孤立の抑制・解消に取り組むための「7つの提案」
- 「7つの提案」と解説
-
-
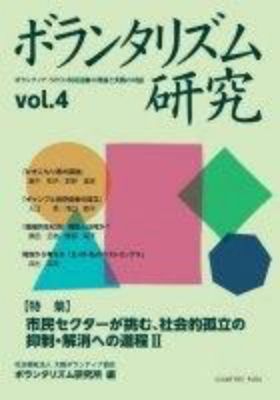
ボランタリズム研究
―Vol.4―特集
市民セクターが挑む、社会的孤立の抑制・解消への道程Ⅱ
発行年2020年10月
「市民セクターの次の10年を考える研究会」第2幕の下記回についてまとめています。
-
第7回 ひきこもり者の孤立 2018/9/24
講師
里中和子さん(ほっとタイム(親の会in藤井寺)代表)
荻野達史さん(静岡大学人文社会科学部教授) -
第8回 ギャンブル依存症者の孤立 2018/10/28
講師
入江泰さん(特定非営利活動法人京都マック生活支援員)
辻井秀治さん(特定非営利活動法人京都マック理事長)
当事者、 家族
滝口直子さん(大谷大学社会学部教授) -
第9回 『地域共生社会』実現への道は? ~住民の「参加」促進はどうあるべきか~
2019/1/6講師
勝部麗子さん(社会福祉法人豊中市社会福祉協議会福祉推進室長)
原田正樹さん(日本福祉大学学長補佐) -
第10回 公・共・私のベストミックス ~ソーシャルワークが切り拓く未来~
2019/1/12講師
井手英策さん(慶応義塾大学経済学部教授)
飛田敦子さん(コミュニティ・サポートセンター神戸事務局長)
-
-

ボランタリズム研究
―Vol.3―特集
市民セクターが挑む、社会的孤立の抑制・解消への道程
発行年2018年12月27日
「市民セクターの次の10年を考える研究会」第2幕の下記回についてまとめています。
-
第1回 子どもの貧困と孤立 2017/1/22
講師
徳丸ゆきこ さん(NPO法人CPAO代表、大阪子どもの貧困アクショングループ代表)
桜井智恵子 さん(関西学院大学大学院人間福祉研究科教授) -
第2回 障害者をめぐる孤立 2017/2/11
講師
みわよしこ さん(フリーランス・ライター)
吉永純 さん(花園大学社会福祉学部教授) -
第3回 高齢者をめぐる孤立 2017/4/23
講師
藤田孝典 さん(特定非営利活動法人ほっとプラス代表理事、聖学院大学人間福祉学部客員准教授)
牧里毎治 さん(関西学院大学名誉教授、関東学院大学客員教授) -
第4回 LGBTをめぐる孤立 2017/6/4
講師
近藤由香(コジ) さん(NPO法人Queer&Women’s Resource Center(QWRC(くぉーく)) 共同代表・理事 )
東優子 さん(大阪府立大学教授) -
第5回 児童虐待をめぐる孤立 2017/7/23
講師
宮口智恵 さん(特定非営利活動法人チャイルド・リソース・センター代表理事
才村純 さん(東京通信大学人間福祉学部教授) -
第6回 外国人をめぐる孤立 2017/9/2
講師
村西優季 さん(NGO神戸外国人救援ネット事務局)
田村太郎 さん(一般財団法人ダイバーシティ研究所代表理事)
-
-

ボランタリズム研究
―Vol.2―特集東日本大震災が市民社会に与えた衝撃 ~市民社会は何を学ぶか~
発行年2013年
- 何ができて、何が問題とされて、何ができなかったのか被災地・者救援活動の現時点での総括
- 被災地における助け合いのボランタリズムはどう機能したのか
- ボランティア:コーディネーションは役割を果たせたのか
- 「フクシマ」を巡る視点
- お金の流れ
-
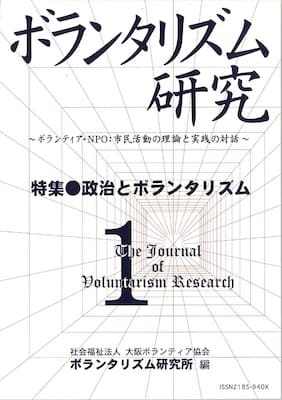
ボランタリズム研究
―Vol.1―特集政治とボランタリズム
発行年2011年
2022年3月、大きくリニューアルして新発行
増補改訂版『ボランティア・NPO・市民活動年表』
増補改訂版『日本ボランティア・NPO・市民活動年表』(大阪ボランティア協会ボランタリズム研究所監修、石田易司・岡本仁宏・永岡正己・早瀬昇・牧口明・牧里毎治・目加田説子・山岡義典編:明石書店発行)が、初版から8年を経て2022年3月に刊行されました。初版の14分野・760ページに新たな事績・知見を加え、16分野13,800項目・1,120ページへと大きく充実。ボランティア・NPO研究や日本の市民活動を推進する上で不可欠な〝知の基盤〟というだけでなく、164編のコラムをはじめ読み物としても楽しめる内容になっています。定価16,500円(本体価格15,000円+税)。
歴史の中のボランタリズムを探る
『ボランティア・NPO・市民活動年表』を読む会
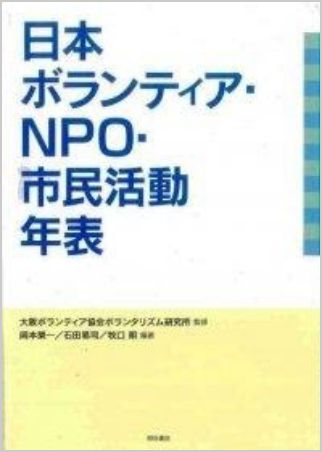
2014年3月発行の初版『日本ボランティア・NPO・市民活動年表』(大阪ボランティア協会ボランタリズム研究所監修、岡本榮一・石田易司・牧口明編著:明石書店発行)は、2015年3月に「第13回日本NPO学会林雄二郎賞」を受賞しました。その学習を通じて市民活動の歴史理解を深めることを目的に、2016年7月から19年3月に計11回の「読む会」を開催。「男女共同参画・フェミニズム」や「平和運動」など14分野の執筆担当者が話題提供し、下記について学びました。
- 1大きな流れ
- 2トピックとなる出来事
- 3研究のノウハウ
市民活動の実践を科学する力をつける
リサーチ&アクション・セミナー
市民活動を行う際には、社会課題を科学的に捉える必要があります。
ニーズの背景にある課題を捉え、それを科学的に分析する「社会調査」の手法や視点を学ぶ
セミナーをNPOや市民活動に携わる人を対象に開催します。
研究者が登壇し調査力・提言力が身につくように話してくれます。
普段の業務や活動を客観的に捉え、ステークホルダーへの発信力を高めます。
市民セクターの次の10年を考える研究会
2013年の公益法人制度改革関連三法の完全施行によって、基本的な達成をみた日本における市民セクターの拡充強化の改革に対する下記の2つの問題意識のもと、次の10年を切り拓く市民セクターの戦略をともに考えていくため「市民セクターの次の10年を考える研究会」を2013年に立ち上げました。
- 1市民活動の水準は高まったのか
- 2自立的な志を持つNPOが持続し、発展できる環境は整ったのか
2017年から19年までの第2幕の成果は「ボランタリズム研究」のVol3、Vol4に、2019年から2022年の成果は「ボランタリズム研究」Vol5(2023年発行予定)に収録予定です。
研究会実績
市民セクターが挑む、社会的孤立の抑制・解消への道程
第2幕-2019年~2022年-
第2幕・第11回~第16回については「ボランタリズム研究」Vol.5をご覧ください。
-
第16回 中間支援組織と政策課題 2022/3/31
講師
実吉威さん(公益財団法人ひょうごコミュニティ財団代表理事/NPO法人市民活動センター神戸理事・事務局長)
大西連さん(認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい理事長/内閣官房孤独・孤立対策室政策参与) -
第15回 社会的孤立と地域組織による対応 2021/9/18
講師
柏木登起さん(一般財団法人明石コミュニティ創造協会事務局長/NPO法人シミンズシーズ代表理事)
後房雄さん(愛知大学地域政策学部教授) -
第14回 社会的孤立と公共政策による対応 2021/7/18
講師
宮本太郎さん(中央大学法学部教授/生活困窮者自立支援全国ネットワーク代表理事)
-
第13回 “お寺というセーフティネット”の可能性-自助・共助・公助・仏助- 2020/1/13
講師
松島靖朗さん(安養寺住職・NPO法人おてらおやつクラブ代表理事)
白波瀬達也さん(桃山学院大学社会学部准教授) -
第12回 <みんな>の参加と協力でつくる“場” 2019/11/2
講師
村上悟さん(特定非営利活動法人碧いびわ湖代表理事)
津富宏さん(静岡県立大学国際関係学部教授) -
第11回 認知症高齢者も安心して住める協働による地域づくり 2019/9/23
講師
中島康晴さん(特定非営利活動法人地域の絆代表理事)
野田真智子さん(株式会社芳林社「Better Care」編集長)
市民セクターが挑む、社会的孤立の抑制・解消への道程
第2幕-2017年~2019年-
第2幕・第1回~第10回については「ボランタリズム研究」Vol.3、Vol4をご覧ください。
-
第1回 子どもの貧困と孤立 2017/1/22
講師
徳丸ゆきこ さん(NPO法人CPAO代表、大阪子どもの貧困アクショングループ代表)
桜井智恵子 さん(関西学院大学大学院人間福祉研究科教授) -
第2回 障害者をめぐる孤立 2017/2/11
講師
みわよしこ さん(フリーランス・ライター)
吉永純 さん(花園大学社会福祉学部教授) -
第3回 高齢者をめぐる孤立 2017/4/23
講師
藤田孝典 さん(特定非営利活動法人ほっとプラス代表理事、聖学院大学人間福祉学部客員准教授)
牧里毎治 さん(関西学院大学名誉教授、関東学院大学客員教授) -
第4回 LGBTをめぐる孤立 2017/6/4
講師
近藤由香(コジ) さん(NPO法人Queer&Women’s Resource Center(QWRC(くぉーく)) 共同代表・理事 )
東優子 さん(大阪府立大学教授) -
第5回 児童虐待をめぐる孤立 2017/7/23
講師
宮口智恵 さん(特定非営利活動法人チャイルド・リソース・センター代表理事
才村純 さん(東京通信大学人間福祉学部教授) -
第6回 外国人をめぐる孤立 2017/9/2
講師
村西優季 さん(NGO神戸外国人救援ネット事務局)
田村太郎 さん(一般財団法人ダイバーシティ研究所代表理事) -
第7回 ひきこもり者の孤立 2018/9/24
講師
里中和子さん(ほっとタイム(親の会in藤井寺)代表)
荻野達史さん(静岡大学人文社会科学部教授) -
第8回 ギャンブル依存症者の孤立 2018/10/28
講師
入江泰さん(特定非営利活動法人京都マック生活支援員)
辻井秀治さん(特定非営利活動法人京都マック理事長)
当事者、 家族
滝口直子さん(大谷大学社会学部教授) -
第9回 『地域共生社会』実現への道は? ~住民の「参加」促進はどうあるべきか~
2019/1/6講師
勝部麗子さん(社会福祉法人豊中市社会福祉協議会福祉推進室長)
原田正樹さん(日本福祉大学学長補佐) -
第10回 公・共・私のベストミックス ~ソーシャルワークが切り拓く未来~
2019/1/12講師
井手英策さん(慶応義塾大学経済学部教授)
飛田敦子さん(コミュニティ・サポートセンター神戸事務局長)
第1幕 ―2013年~2016年―
-
第1回 市民セクターの次なる10年
~ドラッカー・未来の提言を題材に、市民活動の推進の今後のあり方を考える~ 2013/6/15講師
田中 弥生さん(日本NPO学会会長)
-
第2回 中国を通して日本の市民社会を考える 2013/9/29
講師
李 妍焱さん(駒澤大学文学部社会学科准教授)
-
第3回 非営利セクターの課題と展望-公益の認定の経験から 2013/11/2
講師
出口 正之さん(国立民族学博物館教授)
-
第4回 市民セクターができること 2014/1/18
講師
湯浅 誠さん(社会活動家)
-
第6回 ハイブリッド構造としての「社会的企業」とインフラストラクチャー 2014/6/8
講師
藤井 敦史さん(立教大学教授)
-
第7回 『災間の時代』の市民社会論―東日本大震災とネオリベラリズムの後で 2015/2/21
講師
仁平 典宏 さん(東京大学准教授)
-
第8回 日本の参加デモクラシーの現状分析 2015/8/1
講師
坂本 治也さん(関西大学法学部教授)
-
第9回 ボランティア不要論が招くNPOの危機!? ~短期的成果主義と市民参加の軽視を問う 2015/12/13
講師
村上 徹也さん(市民社会コンサルタント)
-
第10回 皆で語ろう!市民セクターの次の10年 2016/1/11
振り返りの素材提供
岡本 仁宏さん(ボランタリズム研究所運営委員長・関西学院大学法学部教授)



 寄付・寄贈する
寄付・寄贈する 寄付する
寄付する 会員になる
会員になる