お知らせ
【CANVAS NEWS】2025年10・11月号
2025年10・11月号 誌面

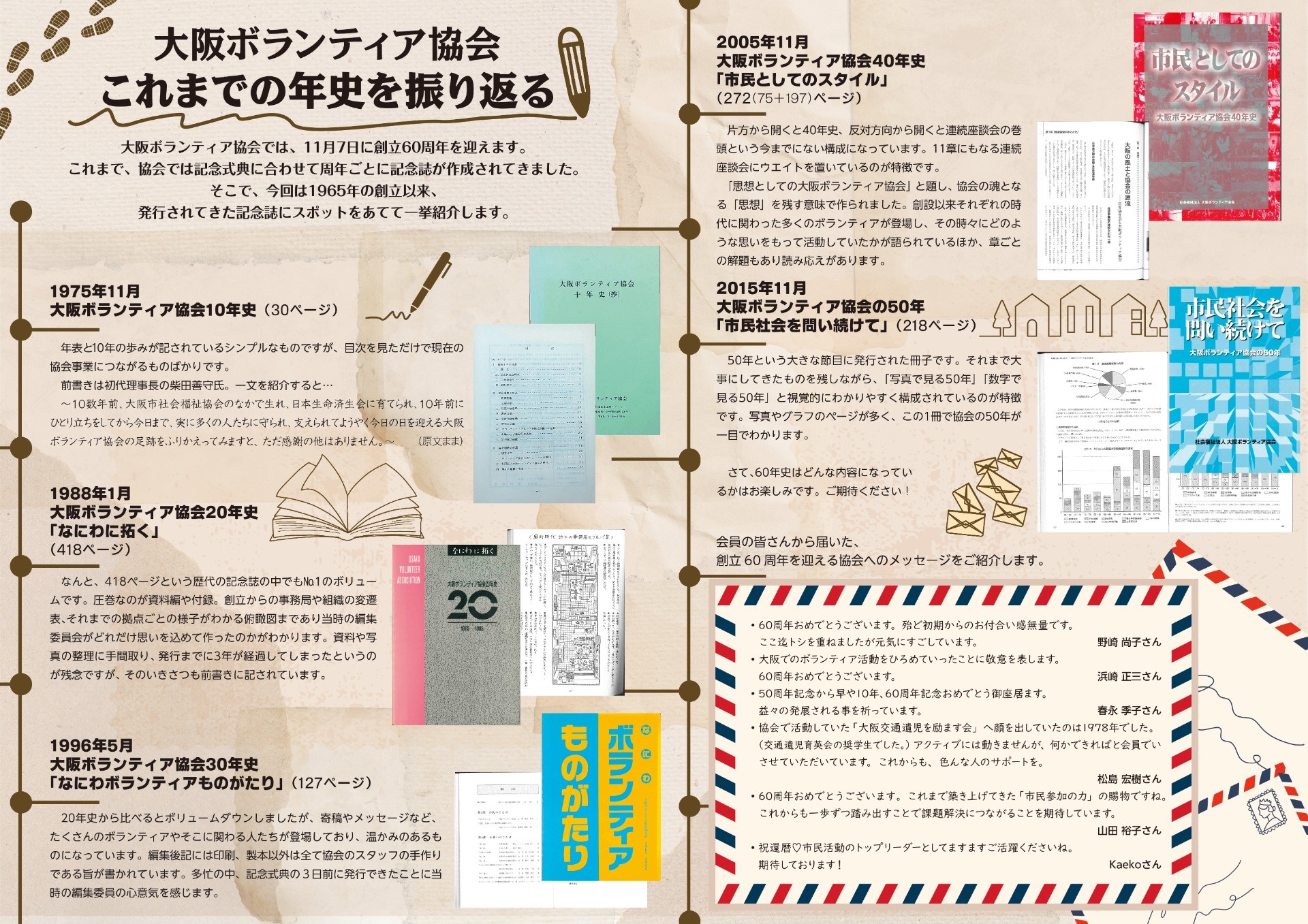
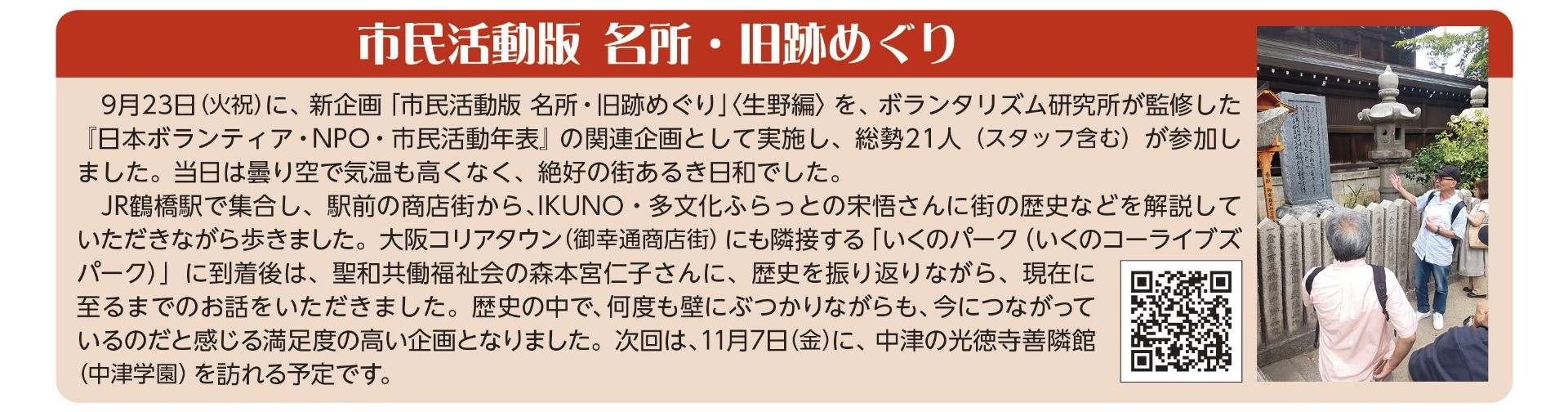
社会課題の解決に向き合うNPO メールインタビュー全文
一般社団法人 コミュニティ・4・チルドレン 桒原 英文さん
1.2011年に「コミュニティ・4・チルドレン(以下、C4C)」が設立されたと拝見しました。設立の背景ときっかけについて教えてください。桒原さんがこの活動を始めようと思われたきっかけや原点をうかがいたいです。
C4C設立前、桒原(代表理事)はフィリピン・ルソン島山岳部で障がい児・者の自立生活支援の活動を、加藤(副代表理事)は生活を成り立てるために出稼ぎに依存している東北タイの村で子どもたちへの奨学金支援を行っていました。地域で子どもたちを支え見守るコミュニティを目指した活動が重要と考え、本会を設立しました。
2.各地での活動は、現地の方々とどのように協働して進められているのでしょうか?特に海外の団体との関係づくりにおいて、工夫されているポイントがあればお聞かせください。
C4Cはタイ・フィリピン・宮城県・カンボジアの地元の市民活動団体や協力者と連携して、それぞれの地域の子どもたちが元気で幸せに成長する取り組みを支え応援しています。海外でも日本でも、どの事業も主体はあくまでも現地の人たちであり、中心となるのはコミュニティです。私たちは現地の方々の力が発揮できるよう、対話を繰り返しながら、情報提供や環境整備、奨学金支援など、伴走しています。また、4か国のそれぞれの実践に学び情報交換するオンラインミーティングも行ってきました。コロナ禍で開催出来なかった4か国のスタッフや子どもたちとの交流事業も再開したいと願っています。
- 3.活動の中で印象に残っている子どもや地域のエピソードがあれば教えてください。また、支援の成果をどのように感じることが多いですか?
どの事業においても、担い手が育ち、担い手となり、実践者としてのコミュニティづくりや生活向上に取り組んでいます。
タイのノーンメック村コミュニティ支援事業では10年以上前から出稼ぎに頼らず、地域で暮らしていける経済力を身につけようと、有機農業に取り組んできました。3年前から米や農産物他を加工した安全な食を提供する月1回のコミュニティ・マーケットを開催し出店する村人の収入につながっています。このマーケットの運営には、以前奨学生だった若者たちが加わっています。マーケットは評判を呼び、他の団体や個人からの依頼もあって移動マーケットを定期的に開催しています。

タイ・マーケットを担う若者
フィリピンのJPCom-CARESの障がい児者自立支援事業では、奨学金を提供していた女の子が山岳部の町の社会福祉開発局のソーシャルワーカーとして地域福祉活動に従事しています。コミュニティの中で子どもたちが育ち、地域づくりの担い手になってきています。HumanBeingが取り組み宮城県を中心とした福祉・防災学習推進事業では、以前は災害と食のプロジェクトに参加していた学生ボランティアサークルのメンバーが、防災×食の学習プログラム・教材開発を同団体の協力者として取り組んでいます。
カンボジアでは、クメール・コミュニティ・ディベロップメントと協働で、子どもたちがボランティアとして、地域の清掃活動や小さな子どもたちの学習支援をしてきました。大きくなって教師となり自分の村の小学校や幼稚園で教員をしている子もいます。有機農業推進事業の研修を受けた小学校校長は、生徒や教員に学校菜園で有機農業を教えています。

カンボジア・有機肥料作り
4.10年以上活動を行われているうえで感じる課題はどのようなものですか。また、今後さらに取り組まれていきたい課題があればお聞かせください。
フィリピンのJPCom-CARESの障がい児者自立支援事業は、これまで自治体の協力を得ることが難しく民間ベースで実施してきましたが、2025年6月にベンゲット州ラ・トリニダット町との官民連携に関する覚書に調印することが出来ました。ラ・トリニダット町内の村々でコミュニティ・ベースのリハビリテーション事業がスタートしています。本会は、町行政、村の関係者と現地団体が協力してすることでスケールメリットが生まれるようサポートしていきます。
タイでは、事業を実施してきた村人たちが高齢化し、少子化が急速に進んでいます。これまでのコミュニティ支援やマーケットづくりの経験を、地元の若者たちにどのように継承していくかが現時点での課題です。彼らの自立を促すためにもソーシャルビジネスも現地の人々と議論していきたいと考えています。
宮城では東日本大震災の発生から15年近くが経過する中、震災からの教訓をどのように次世代につないでいくかが課題となっています。HumanBeingでは、当時の経験や教訓を元にした防災学習教材を製作しています。来年3月には、15年間の活動のあゆみを発行予定です。
これまでタイでの研修中心で実施してきたカンボジアの有機農業推進事業は、生産物の販売促進が重要な段階です。現地パートナーや自治体等と協働して、活動の幅が広がるように支援していきます。

フィリピン・ラ・トリニダット町との覚書調印式
5.C4Cの活動を通じて、子どもたちに一番伝えたいことは何でしょうか。
笑顔で夢を持って成長して欲しいです。将来、自分の持つ力を活かして、時には他者を励まし、住む地域をより良いものにするために、自ら行動できる大人になって欲しいと願っています。
6.今後の展望を教えてください。
今後も4か国の取り組みの自立性を高めるために出来る限りの社会資源の提供をすると共に、協働実践に取り組んでいきます。
特定非営利活動法人 ほのぼのステーション 加藤 邦子さん
- 1.団体設立のきっかけや経緯を教えてください。
堺市役所で常勤、非常勤として働くヘルパーが中心となって趣旨に賛同する保健師、社会福祉士が理事となり、2002年9月にNPO法人を立ち上げました。当時堺市でNPO法人はまだ10くらいでした。大きなきっかけとなったのは「地域通貨」との出会いでした。大阪大学で行われた寄付講座をきっかけに「地域通貨」は地域やグループ内で「お礼の気持ち」をあらわすツールとしてすごく有効だとひらめき、私たちも「地域通貨ほのぼの」を作って活動を始めたところあちらこちらから問い合わせがあり、ネットワークが広がりました。社会福祉協議会の助成金で冊子「やってみたよ!地域通貨」を発行しました。
2.団体の活動内容について簡単に教えてください。
法人の事業としてまず取り組んだのは精神障害者へのヘルパー派遣事業でした。介護保険とは違い、費用弁済方式の制度は始まったばかりで堺市の保健センターから丁寧な指導やケースの紹介があり、堺市直営のヘルパー派遣制度をやめたために仲間のヘルパーがたくさん登録してくれ、あっという間に事業が軌道に乗りました。そこでヘルパーだけでなく拠点施設を持ちたいと考え、介護保険の新しい事業である「小規模多機能型居宅介護事業」に取り組むことにしました。何千万円もの資金をどうしたのかと周りからよく聞かれましたが、仲間の出資や日本財団の助成金、土地を担保にした銀行の借り入れで賄うことができました。
振り返ってみれば私たちの法人がこのように続けてこられたのは、まずいつも新しいことに取り組んできたからだと思います。地域に知ってもらうためミニ喫茶「集い場」も開きました(ボランティアで運営しています)。この25年の間、大阪ボランティア協会からたくさんの支援や物品の寄付をいただき、企業からの助成金も数多くいただきました。

3.「ひとのえき ほのぼの」は2023年に新たに開所されたと拝見しました。長年の活動の中で、新しい事業を立ち上げられた想いをお聞かせください。
2009年の「小規模多機能型居宅介護事業・ほのぼの旭ヶ丘の家」は開所以来徐々に重度の利用者が減り、ヘルパー事業も報酬単価が切り下げられ、職員を募集しても応募はなく、法人の収益もだんだん赤字になってきました。そんな中、高齢者の住む場所の必要性を感じていた私たちはこの危機を乗り切る道として「高齢者と若者のシェアハウス」を企画したところ、なんとメットライフ財団の助成事業に採択されることになりました。2023年12月2日「ひとのえき・ほのぼの」はこうしてオープニングを迎えることができました。
今は総合事業として各市町村で取り組まれている“担い手型通所サービス”とシェアルームを運営しています。リビングはレンタルスペースとして貸出もしています。ここもボランティアで運営しています。ボランティア仲間の居場所にもなっています。


4.今後の課題についてお聞かせください。
ボランティアもスタッフも高齢化しています。次の法人の担い手を全力で育成し、バトンタッチすることが現在の課題です。



 寄付・寄贈する
寄付・寄贈する 寄付する
寄付する 会員になる
会員になる

